パプリカ ― 2025/03/22 23:47
□パプリカ(筒井康隆 1993)
この前観たアニメ映画が面白かったので原作も読んでみた。
小説は、映像命のアニメと違い言葉でたっぷりと説明できるので、夢探偵の理屈もそれらしく説明されている。作者の精神医学方面の蘊蓄と疑似科学を適度にブレンドしたほら話の醍醐味がたっぷり味わえるSFであった。作品中でフロイトを時代遅れと批判しているが、作者の本音なのであろうか?
小説を読んで分かったのは、アニメは結構原作を忠実に再現していたんだなと言うこと、無論、2時間弱の映像作品として収めるための、筋やキャラクターの整理や誇張はあるが概ね同じであった。しかし、悪役は、はるかに原作の方が、文字通り悪魔的で魅力的であった。映画化したのは、既に多様性尊重の21世紀、あのキャラをあのままで世に出すのは無理であったろうな。
パプリカ ― 2025/03/04 18:46
□パプリカ(今 敏監督、筒井康隆原作 2006)
肌寒い雨の日は古いアニメでも見ようと思って、駅前の映画館に行った。
他人の夢の中に入り込めるサイコセラピストの冒険談、一応、マッドサイエンティスト発明の最新インターフェースの力を借りてと理屈付けしてあるが、どんどん夢と現実の境がなくなってくるので、見ている分には超能力活劇である。
つまり、「AKIRA(1988)」や「攻殻機動隊(1995)」の系譜を継ぐ、超能力アニメと言ってよいと思う。19年前のアニメだが、筋立ても作画も古びていないので、違和感なく楽しめた(二つ折りのケータイはでてくるけど)。
主人公たちが幸せになるハッピーエンドだったけど、筒井康隆の原作も本当にそうなのか、今度読んで確かめてみよう。なお、この映画と同名のヒット曲(米津玄師 2018)とは関係なさそうだ。

イメージ写真
宇宙戦艦ヤマト ― 2025/02/22 19:50
□宇宙戦艦ヤマト 黎明編2(塙 龍之 2024)
「宇宙戦艦ヤマト」のアニメ以降の物語、2021年に出た「黎明編 アクエリアス・アルゴリズム(高島雄哉)」の続編にあたる。黎明編「2」と言うからには、複数の書き手によって今後も書き継がれ、サーガとなる見込み(思惑?)のようだ。
氷惑星に閉じ込められたヤマトの再起動を描いた前作が、SFとしてはやや期待外れと感じたのに、続編をまた手に取ってしまったのは、ヤマトと言う名前の記号的魔力のなせる業か、それとも表紙のド直球なイラストの所為か。
結論から言うと前作より遥かに面白く読めた。ファンジン出身の新しい著者の「ヤマト」に込める思い入れ、熱量が強いのかもしれないが、名敵役デスラーを陰にちらつかせる巧みなストーリーとテンポの良さに引き付けられた。
ただ、野暮を承知であえて言うと、量子重力論的な幽霊を宇宙で活躍させるには、もう少し嘘なりの理屈を書き込んでほしかった。もっとうまくやれば、古典的SFの醍醐味、センスオブワンダーも味わえたのに、と思う。
つまり、そこを補強した「3(又は成長編等)」が出れば、また読んでしまうかも。

これはペンです ― 2025/01/17 22:20
□これはペンです(円城 塔 2011)
今、最も評判の良いSF作家の一人らしい円城 塔の本を初めて読んだ。
・これはペンです
・良い夜を持っている
の中編2作が載っていた。
正直、読みにくかった、特に最初の頁から順繰りに筋を追おうとすると、頭が混乱してきて一時は読むのを止めようかと思った。ところが、止めるのも勿体ないのでランダムに拾い読みすると、部分部分は結構面白く、結局、するすると全部読んでしまった。そういう構造の小説かもしれない。
2編とも、ざっくり言ってしまえば、家族と言葉の物語である。
なんとなく、昔大学で読まされた記号論理学の教科書を思い出した。東大大学院総合文化研究科で博士号を取得した、作者の経験から来るものかもしれない。偶然にも、最近読んだ福岡伸一の「生物と無生物の間(2007)」に出ていた、DNAの4語の塩基(A,T,C,G)の話も出てきた。

生物と無生物の間 ― 2025/01/15 21:03
□生物と無生物の間(福岡 伸一 2007)
生物学者の書いたポピュラーサイエンス、遺伝子と生物に関する入門書とも、野口英世の功罪に垣間見える研究者人生のアイロニーを書いたエッセイとも読める。その所為か、出版時には理系の解説書としては珍しくベストセラーになった由。
一番印象に残ったのは、遺伝子がたった四種の塩基(A:アデニン、T::チミン、C:シニン、G:グアニン)で構成されているという事実、知ってる人には常識なのだが、素人には、我々の設計図がたった四文字で書かれていると言うのは驚きだった。
筆者の主張は、生物の特徴は、増殖に加えて、絶え間なるエントロピーの趨勢に抗う動的平衡であるというもの。つまり、ウィルスは生物とは認めない。
じゃ、僕を苦しめたあれは、なんなんだと、コロナに罹った僕は思う。

地球外の石 ― 2024/12/18 20:28
□小惑星からの3サンプル同時公開@国立科学博物館
無人探査機「はやぶさ」、「はやぶさ2」および「オシリス・レックス(NASA)」が小惑星(夫々「イトカワ」、「リュウグウ」、「ベヌー」)から持ち帰った3サンプル(砂粒)を科学博物館で公開していたので見に行った。
せいぜい数ミリのサンプルなので、肉眼で見るというよりは顕微鏡のモニター(イトカワのサンプルは微小なので電子顕微鏡)を見る感じだが、はるばる宇宙から来たと思うと満足感があった。行く気はないが、大阪万博で展示予定の火星の石というふれこみの隕石よりは見る価値があるのではないか。
文字通り天文学的な費用をかけて持ち帰った貴重なサンプルなので、さぞや見物人が押しかけて混んでいるかと思ったが、見た目は溶岩のような黒い砂粒という地味な展示品なので、人はスカスカ、じっくりと見ることが出来た。常設展示室なのでシニアの僕は入場無料であった。
これも眼福と言うのだろうな。




クオリティランド ― 2024/11/17 13:25
□クオリティランド(マルク=ウヴェ・クリング/森内 薫(訳) 2019)
巨大なAIパワーを誇る、グーグルやアマゾン、Xを想起させる独占企業群が睥睨的に個人情報を収集管理選別利用している、近未来のドイツと思しき「クオリティランド」、その究極のマーケティング本位国家に、ドン・キホーテのごとく立ち向かう下層市民ペーター・ジョブレス(無職のペーター)の活躍を描く冒険談。
なんとなくトランプを思わせる大統領候補や、アンドロイドの対立候補も出てくる。主人公の恋人の名はキキ、宮崎アニメ「魔女の宅急便(1989)」の主人公と同名だ。
AIの社会への浸透の程度などは、本書の出版当時はまだSFだったのだろうが、今は完全に現実だなあ。
ちなみに、本書の世界では、マッチングアプリ(デーティングアプリ)は公式には、クオリティ・パートナー、俗語的にはファックファインダーと呼ばれる。
ドイツSF大賞第一位(2018)。

八犬伝 ― 2024/10/28 19:23
□八犬伝(曽利文彦 監督 2024)
かのジュサブローのNHKテレビ人形劇「新八犬伝(1973-75)」に魅せられた曽利監督が、山田風太郎の原作「八犬伝(1983)」に出会って作り出した幻想時代劇。
映画は、作り物、「虚」である八犬伝の物語と、戯作者、滝沢馬琴が画家、葛飾北斎と交流しながら物語を紡ぎだす「実」の過程が交互に展開しながら、虚実の被膜で人は何故物語るのかを語る、物語の物語、メタフィクションとなっている。
物語八犬伝の場面は、監督お得意のVFXも駆使した爽快なチャンバラとおどろおどろしい玉梓が怨霊が楽しめる。一方、映画の中での実話である馬琴(役所広司)と北斎(内野聖陽)の掛け合いでは、名優の演技が楽しめる、が少し長い。
とても面白い映画だったが、かつての薬師丸ひろ子@「里見八犬伝(1983)」のような圧倒的アイドルが出演していないせいか、入りは今一だった。もっと観てほしい。

タイムスリップ忠臣蔵 ― 2024/10/18 20:18
□タイムスリップ忠臣蔵(鯨 統一郎 2012)
赤穂浪士の討ち入りが無かったもう一つの日本では、生き延びた吉良上野介が犬公方徳川綱吉のお先棒を担いでお犬様ファーストの政治を進め、それがために犬が驚異的に進化増長し、遂にはテレパシーで人を支配するお犬様帝国になっていた。
この犬の支配から人類の未来を取り戻すため、美少女三剣士が江戸時代にタイムスリップし、大石内蔵助を叱咤激励して主君の仇、犬社会を招いた元凶たる吉良を討たせるというトンデモなSF時代劇。
うむ、ばかばかしくて面白かった、山田風太郎の趣あり。

新・世界の七不思議 ― 2024/10/11 17:05
□新・世界の七不思議(鯨 統一郎 2005(文庫版))
森鴎外がタイムスリップした話は面白く、聖徳太子がタイムスリップした話は手抜きだった、鯨 統一郎のたぶん原点に近い素質が味わえる短編集、というか世界の七不思議をネタにした屁理屈のオンパレード。ストーンヘンジ=鳥居説など、すべての謎が日本に行きつく処が凄い。
それにしてもこの人の名前が凄い、ペンネームだと思うけれど、一体何を「統一」しようとしているのであろうか?
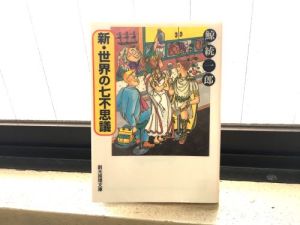
最近のコメント